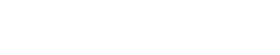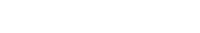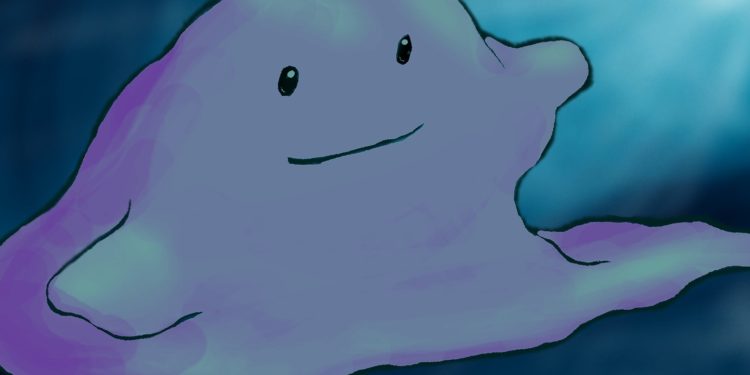我が家族よ、どうかそのままで…
寄稿者:マツゴ(86歳 男性・エンジンシティ)
私の人生というものはかくして平凡の一言である。
しかしそんな平凡な人生でも宝物ができた。私にとってそれは家族であった。若いときの私はそれはそれは愚かであった。仕事にかまけ家族は二の次。それはひどい男である。
私には妻がいた。こんなわたしにも甲斐甲斐しく世話を焼き、それはいい女房だった。それでも私はその頃大きな商談もあったことも相まって家庭や家族のことを頭から追いやっていた。
◇
そんなある日のことである。職場にかかる一本の電話。妻が倒れたとの報である。何事かと病院にかけつける私に、神から鉄槌が下された。医者の口を借りて。
奥様の一命はとりとめましたが、子どもは助かりませんでした。出血が多く、子宮も残念ながら残されませんでした、と。
私は衝撃を受けた。
ちょっとまて、子どもなんて私は一言も聞いてないぞ、一言も…。いや、聞いてないんじゃない、妻は言えなかったんだ。私がそばにいなかったから…。それから猛省し、私は妻の看病に乗り出した。
しばらく元気がなかった妻がある日私に初めてワガママを言った。
「メタモンと暮らしたい」と。
何故メタモン?と思ったが私はすぐさまメタモンを探し友人から譲り受けたのである。
ある日、私は仕事が入り、外に出る機会があった。しかし思ったより早く用事がすみ帰宅したのである。すると私は信じられないものをみた。家に赤子がいるではないか!妻が笑っている…
私はすべてを察し、身を丸め慟哭した。
妻はメタモンを赤子の姿に変え、心の傷を癒やしていたのだ。どれほど私は無力なのだ…。わたしは思わず妻に駆け寄りこういうしかなかった。
「すまない、すまない、、、」と。
私は愚かな夫のまま、心身ともに衰弱した妻は後日、旅立ったのである。
◇
そして虚無の日々を送り、今度は私の番、というわけである。私は今、死の床にいる。私は妻のそばにいけるのだろうか?ああ、妻が迎えにきた…。
そう思った瞬間はっとした。
妻が確かに私の手を握っているのである。
これは夢か誠か。
と思ったが私には全てわかっていた。
「メタモン…」
そう、メタモンが妻になっていた。
その瞬間私は走馬灯をみた。
そうだ、あの虚無の日々にもメタモンがいた。メタモンは全てわかっていたのだ。私が妻を失ったことも。罪悪感と寂しさの日々も。でなければどうして今、妻の姿になろうか…
「メタモン…、もういいんだ」
メタモン、お前は間違いなく私の家族だ。私の悲しみを理解し、お前も悲しんでいたんだな…
「ありのままのお前でいい」
少し躊躇したメタモンが、もとの姿に戻っていく。どうかメタモン、忘れるなとは言わない。でも、もう誰の替わりにもならなくていいんだ。
どうかそのままで…。